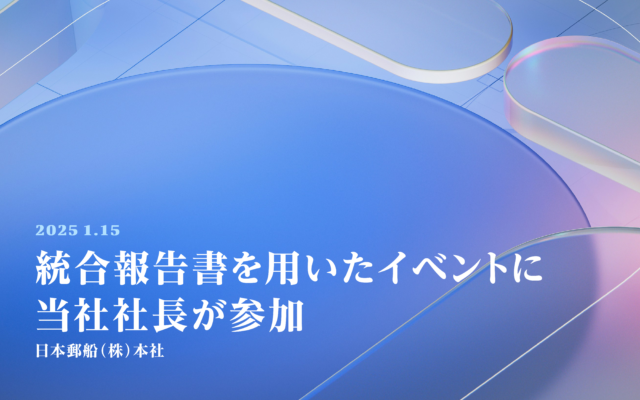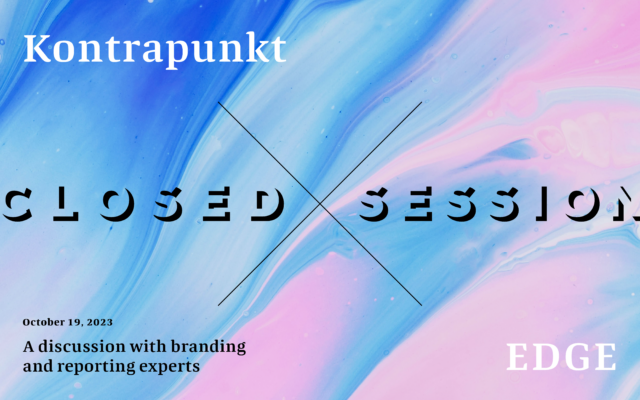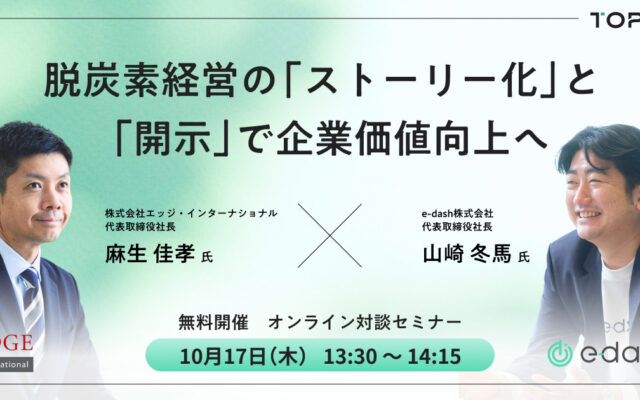統合報告書2023年版調査 ~マテリアリティ~

EDGEリサーチ・インスティテュートは、「統合報告書2023年版調査 ~マテリアリティ~」の結果を公開しました。当社運営の企業価値レポーティング・ラボでは、統合報告書を発行する日本企業を毎年調査してきました。それら企業のうち上場企業を対象に、マテリアリティ開示の現状について調査・分析を行ったもので、7回目の調査となります。本調査は、企業と長期投資家のよりよい対話に向けた示唆になるものと考えています。
なお、本調査のローデータや詳細につきましては、ご希望いただきました機関投資家や研究者の皆様には、情報提供させていただきます。
■調査目的
統合報告書を発行する日本企業が「マテリアリティ」についてどのように開示しているか、現状を把握する。
■調査概要と結果
自己表明型統合報告書*1 を発行している日本の上場企業を対象に「マテリアリティ」に関連する下記の要素について、統合報告書における開示の有無を調査した。
なお、2023年調査より調査項目数を絞り込み、分析に比重を移した。
①マテリアリティを開示:87.8%(828社)
②企業価値視点のマテリアリティを開示:73.4%(692社)
③②について機会とリスクに分けた開示:16.5%(156社)
④環境・社会視点のマテリアリティを開示:75.4%(711社)
⑤④についてポジティブ及びネガティブインパクトに分けた開示:0.7%(7社)
⑥②と④両方の視点を考慮したマテリアリティを開示:60.4%(570社)
⑦⑥において同じリストだが視点の区分を明確に開示:2.5%(24社)
⑧⑥においてそれぞれ別のリストで開示:0.5%(5社)
※マテリアリティという言葉を使用しない類似表現でも、内容が該当していれば抽出している。
※特定されたマテリアリティについて妥当性は問わない。
*1 企業価値レポーティング・ラボ(運営:株式会社エッジ・インターナショナル)が調査している「国内自己表明型統合レポート発行企業リスト 2023年版」の1,017社のうち、日本の上場企業943社を対象。
https://www.edge-intl.co.jp/wp-content/themes/edge-intl/assets/pdf/01_reserch/02/list2023_J.pdf
■考察
「マテリアリティ」は、あらゆる企業報告における基本的な概念で、発行体に対する読み手の評価や分析結果に差異をもたらす情報やその判断基準を指すが、その情報の主たる利用者について、投資家と、投資家を含むマルチステークホルダーの二つに大きく分けられる。投資家の投資哲学や手法は多様であるが、メインストリームの長期機関投資家を想定した場合においては、それぞれフォーカスする視点は、投資家は企業価値、マルチステークホルダーは環境・社会であると言い換えられる。また本調査においては、「マテリアリティ評価に基づく課題/テーマ」を「マテリアリティ」と表現している。
先に挙げた二つの視点のいずれか、または両方の視点からマテリアリティを統合報告書で開示している企業は87.8%(828社)であった。2022年に前年から大幅に増加したが、そこからさらに増加となった。この6年で、マテリアリティは統合報告書の中で標準的な開示要素として定着したと考えられる。
「企業価値視点のマテリアリティ」を記載したレポートは73.4%(692社)であった。マテリアリティについて、企業の中長期的な価値創造の実現への影響、または、ビジネスモデルの持続性の担保や財務パフォーマンスへの影響を意図して特定された企業をカウントしている。企業価値視点のマテリアリティを機会とリスクに分けた説明の開示は16.5%(156社)で見られた。
一方、「環境・社会視点のマテリアリティ」は75.4%(711社)で記載があった。サステナビリティ報告の開示基準であるGRIが要求する「マテリアルな項目」に準拠したもので、いわば「事業活動によって著しい悪影響を及ぼす課題」や「事業を通じて解決に貢献できる社会課題」の優先付けがなされている事例をカウントした。
環境・社会視点のマテリアリティを社会的なポジティブインパクトやネガティブインパクトの観点から説明する事例は0.7%(7社)と、ごく少数にとどまった。
「企業価値視点」と「環境・社会視点」の両方の視点から特定したマテリアリティを掲載しているレポートは60.4%(570社)であった。大半が両視点を加味したマテリアリティ、つまりダブル・マテリアリティの考え方で特定されていた事例だったが、同じマテリアリティリストとして開示しつつも、両視点の区分が明確な事例は2.5%(24社)であった。一方、「企業価値視点」と「環境・社会視点」の各視点で特定したマテリアリティを、異なるページなどで別のリストとしてそれぞれ開示している事例は0.5%(5社)であった。
「企業価値視点のマテリアリティ」は前年の65.6%(537社)から7.8ポイント増加し、進展が見られた。「環境・社会視点のマテリアリティ」についても前年の70.1%(574社)から5.3ポイント増加となった。両視点でマテリアリティを開示する事例は、前年の50.1%(410社)からさらに10.3ポイントの増加となった。
変化率で見ると「企業価値視点」の方が増加幅が大きく、投資家からのニーズに応える形でマテリアリティの開示が広がってきていると考えられる。しかし実数としては「環境・社会視点」の方が未だ多い結果になった。また両視点の開示事例も増加しており、開示が進む中でもシングルではなく、ダブル・マテリアリティのスタンスをとる企業がさらに増えていることも確認された。
一方、企業価値視点のマテリアリティを機会とリスクに分けた説明の開示は前年の18.8%(154社)から2.3ポイントの減少となった。環境・社会視点のマテリアリティについて社会的インパクトの観点から説明する事例も前年の1.1%(9社)から0.4ポイント減少し、さらに少数となった。
マテリアリティの開示は進んでいるものの、企業価値評価に反映しやすい要素である機会・リスクやインパクトについての具体的な説明がなされていない事例が未だ多いという課題が浮き彫りになった。
またダブル・マテリアリティの事例は増加したものの、財務と環境・社会インパクトのそれぞれの視点を明確に区分している事例は少数にとどまったままであり、様々なスタンスをとる投資家の情報ニーズを満たせていないという懸念が残った。
統合報告書におけるマテリアリティの開示は本調査を開始した6年前から急速に拡大した。また以前はGRIに基づく環境・社会視点が主流で、企業価値視点のマテリアリティは少数派であったが、投資家が求める視点である企業価値視点を取り入れた事例が大半を占めるようにもなった。開示が定着したという意味で、定点観測を行ってきた本調査は一定の役目を終えたと考えられる。
しかしマテリアリティ開示の伸び率と比較し、機会・リスクの説明の開示は増加しているものの、大きな変化にはなっていない。これは多くの会社でマテリアリティ評価分析が曖昧に行われており、マテリアリティが「開示のための開示」になってしまっている可能性を示唆している。それでは真に有用な開示情報とならず、開示を起点とした経営変革を促す効果も期待できない。
経済産業省の資料によれば*2、価値創造ストーリーを伝えるという本質的な開示が十分できている統合報告書ばかりではないとされている。統合報告書は有価証券報告書と比較し、各種の表彰制度等が存在することに加えて、投資家からの評価・意見を直接確認できる機会も多く、企業内でPDCAサイクルがうまく回り、年々改善が図られているとの指摘もある。部分的もしくは表面的な改善は図られているものの、全体としては本質的な改善につながっていない企業が多くいると推察される。
今後、ISSB基準の強制適用や欧州CSRDの施行に伴い、サステナビリティ情報開示対応としてのマテリアリティ評価が必須となる。これまでは任意開示にも関わらず、形式的な記載内容が多く、形骸化という負の側面が顕在化していたが、義務になればよりその傾向は強まることが懸念される。
日本のコーポレートガバナンス改革においては、開示をドライバーとして経営変革を促す政策がとられてきた。その結果、開示は拡充し、一部の企業で経営変革も見られたが、全体としてはまだ課題が多く残っているとの課題認識*3 がある。
開示が経営変革のドライバーとして機能するためにはどうすべきか、本稿ではマテリアリティ開示をキーとして、対外開示/経営変革の両側面から検討してみたい。
対外開示としての質を上げていくためには、特定したマテリアリティについて機会とリスクの説明を充実させるべきであると考える。これはISSBでも改めて重要性が指摘されている、企業価値との「つながり」を示すという観点とも重なる。投資家からよく指摘される情報開示の課題にも、「サステナビリティ情報が企業価値にどのようにつながるのかが不明瞭」という点がある。
すでに多くの情報を開示している場合、全ての情報を緻密につないでいくことは容易ではない。またビジネスモデルが複雑な場合も、価値創造ストーリーをシンプルに伝えることは難しいかもしれない。まずは絞り込まれた事項であるマテリアリティから「つながり」を示していくことに挑戦することで、価値創造ストーリーを強固にする象徴的なコンテンツになりうるのではないか。そのためには経営陣の認識としての機会とリスクを、充実した情報の質と量で、マテリアリティと併せて開示することが必須だと考えられる。
またサステナビリティ情報の制度開示化に伴い、ISSBやESRSにもマテリアリティ評価についてのガイダンスが示されている。特定されたマテリアリティやその機会とリスクには企業特有の事情を背景とした独自性があるべきだが、特定プロセスは最新のガイダンスを用いて標準化された対応をベースとすることで、より高品質な情報開示につながると思われる。
経営変革を促す社内コミュニケーションへの活用としては、社内議論の活性化のきっかけとすることが想定される。マテリアリティ開示実務とともに、マテリアリティ特定プロセスにおける経営陣や社内ステークホルダーの関与も定着したと推察されるため、その見直しの過程でより一層踏み込んだ議論を行うことが望まれる。統合報告書の黎明期に部門間のサイロを壊すという効果が期待され、実際にその効果は多くの企業で表れた。統合報告書は会社全体で経営改善について話せる機会になったとしている会社もある*4 。マテリアリティに議論を絞ることで、統合報告書制作時よりも部門横断での議論がよりシャープになり、経営変革へ直結しやすくなることが期待される。
*2 経済産業省 企業情報開示のあり方に関する懇談会 課題と今後の方向性(中間報告)(2024.6)
*3 経済産業省 持続的な企業価値向上に関する懇談会(座長としての中間報告)(2024.6)
*4 経済産業省 第2回 企業情報開示のあり方に関する懇談会 事務局資料(2024.6)
また、社外ステークホルダーの声を定期的に取り入れるプロセスとしての活用も想定される。マテリアリティは年次、もしくは外部環境の変化に応じて定期的に見直すことが求められる。マテリアリティの特定、特に環境・社会インパクトを評価する際には社外のステークホルダーの関与は肝要となる。経営環境の変化が大きい昨今においては、マテリアリティ評価プロセスを自社の環境・社会インパクトについて社外のステークホルダーと議論する機会とすることは、期待に応えていくことのみならず、SXにつながるような経営変革にとっても有用なインプットを取り入れることを仕組化することができる。
コーポレートガバナンス改革の開始から一定の年月が経過し、またサステナビリティ情報開示の義務化という企業報告にとっては大きな転換期を迎えている今、より「実践」に直接的につながるような「開示」の改善を期待したい。